AIO・LLMO・GEOとは?SEOとの違いと対策方法やパートナー会社選びを解説
2025年6月5日
東証スタンダード上場企業のジオコードが運営!
SEOがまるっと解るWebマガジン
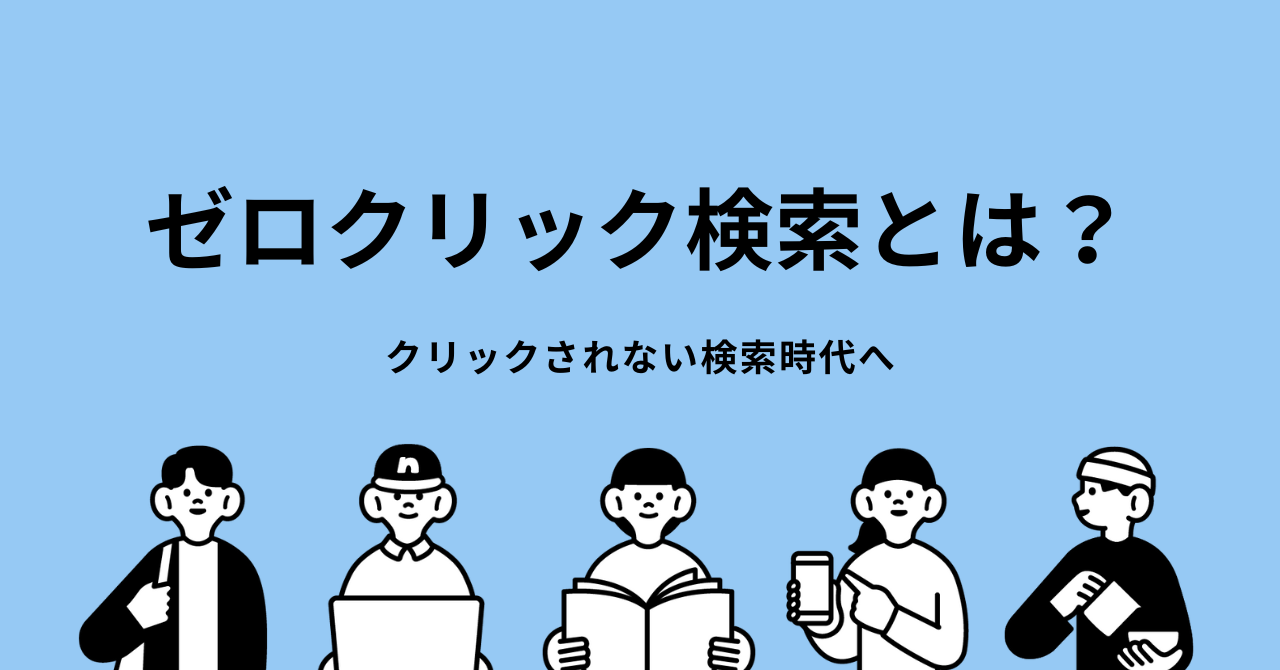 ゼロクリック検索とは?クリックされない検索時代とSEOの新戦略
ゼロクリック検索とは?クリックされない検索時代とSEOの新戦略

【監修】株式会社ジオコード SEO事業 責任者
栗原 勇一
検索体験が大きく変わり始めています。
Googleをはじめとする検索エンジンでは、ユーザーがサイトにアクセスせずとも情報を得られる「ゼロクリック検索」が急増。さらに、生成AIを活用したAI Overviews(AIO)や、LLMO(Large Language Model Optimization)といった概念の登場によって、「クリックされる前提のSEO」はすでに通用しなくなりつつあります。
こうした変化は、企業のWeb集客戦略に大きな影響を与えています。
とくにBtoB領域や高単価商材では、1クリックごとの価値が高いため、検索結果から直接ユーザーに情報が伝わってしまうことは機会損失にもなりかねません。
本記事では、「ゼロクリック検索とは何か?」という基礎から、AIO・LLMOによってどう変化しているのか、そして今後のSEOにどう向き合うべきかまで、わかりやすく解説していきます。
ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索エンジンでキーワードを入力した際に、検索結果ページ上で疑問が解決されてしまい、どのウェブサイトにもクリックせずに離脱する現象を指します。
Googleが強調スニペットやナレッジパネルなどの表示を強化したことで、ユーザーはページ遷移することなく、必要な情報を得られるようになりました。
たとえば、「東京 天気」「1ドル 円」「社長の名前」などの検索では、ページ上部に直接答えが表示されるため、ほとんどのユーザーはリンクをクリックしません。
ゼロクリック検索が増加している背景には、Googleのユーザー体験重視の方針があります。
ユーザーが求める情報を“最速”で提供することが検索エンジンの価値であり、その結果として、検索結果画面自体が「情報のゴール」になるケースが増えているのです。
さらに、モバイル検索の普及も大きな要因です。画面サイズが限られるスマートフォンでは、ファーストビューで答えが見えると、下にスクロールして他サイトを閲覧するモチベーションが下がりやすい傾向があります。
以下のような検索結果が、ゼロクリックを引き起こす代表例です。
・強調スニペット(Featured Snippet)
検索キーワードに対する答えを、Googleが特定のページから抜粋して上部に表示する形式。
例:「SEOとは」で検索すると、説明文が検索結果に直接表示される。
・ナレッジパネル
有名人や企業などの情報を、右側にまとめて表示。情報元はWikipediaやGoogleの独自データベース。
・天気・為替・電卓・スポーツのスコアなどのウィジェット
即時性が求められる情報については、Googleが専用モジュールで答えを提示。
これらは一見ユーザーにとって便利な機能ですが、従来の「クリック=流入」というSEOモデルにとっては逆風とも言えます。
ゼロクリック検索の増加は、ウェブサイトへのトラフィック減少をもたらす要因のひとつです。
とくにFAQ型のコンテンツや定義解説ページなど、検索意図が「即答を求める」タイプのキーワードでは、上位表示されていてもクリックされないケースが増えています。
ただし、ゼロクリック=悪とは言い切れません。
強調スニペットやナレッジパネルに自社が取り上げられることで、ブランド露出や信頼性の向上といった副次的な効果も得られます。
クリックされなくても、検索体験の中でユーザーとの接点を持てるなら、それは一種の「成果」として考える必要があります。
ゼロクリック検索においても、「表示領域(プレゼンス)」を制する者が勝つという考え方が有効です。
具体的には、以下のような施策がポイントになります。
①構造化データの実装(Schema.org):Googleに内容を正確に理解させ、強調スニペット表示のチャンスを広げる
②FAQ・HowToページの強化:ゼロクリックが起こりやすいキーワード群に対して、1位・抜粋対象を狙う
③視認性の高いブランド名・ロゴの記載:情報の信頼性が“誰の発信か”で判断されやすいため、認知向上にもつながる
表示されたうえでクリックされなかったとしても、情報源としての存在感を出すことは長期的な信頼構築に寄与します。
これからのSEOでは、単なる「アクセス獲得」ではなく、**“表示されたときにどれだけ印象を残せるか”**が重要になります。そこで意識したいのが以下のポイントです。
①検索意図に対して端的に答えるパートを明示する(例:記事冒頭に要約ボックスを設ける)
②ブランド・サービスへの興味を自然に引き出す導線を入れる(例:関連ページへの内部リンクや、参考資料の案内)
③専門性・独自性を担保するデータ・視点を含める(ゼロクリックになりにくい深掘り型の要素)
④ゼロクリックが増えても、“あの会社の発信だから信頼できる”という認知が生まれれば、次の検索や比較フェーズで優位に立てる可能性が高まります。
2024年以降、Googleが本格展開を進める「AI Overviews(AIO)」は、検索体験に大きな変化をもたらしました。
AIOとは、検索キーワードに対して生成AIが複数サイトの情報を要約し、回答を検索結果の上部に表示する機能です。
この仕組みにより、従来の強調スニペット以上に「検索結果で答えが完結」する傾向が強まり、ユーザーがリンクをクリックする必要性はさらに低下しました。
AIOはゼロクリック検索の進化系とも言える存在であり、SEOにとっては新たな競争環境の幕開けとも言えます。
AIOに加えて注目されているのが、**SGE(Search Generative Experience)**に代表される、生成AIによる検索の再構築です。
ユーザーはキーワードを入力するだけでなく、対話型で疑問を深掘りできるようになり、検索結果に表示されるコンテンツの意味も変わってきています。この文脈では、次のような変化が起きています。
・情報が「引用」されること自体が目的化する(クリックされなくても引用元として認知される価値)
・コンテンツの網羅性よりも“要点と信頼性”が重視される傾向
・会話文脈で取り上げられる表現や構造が重要になる(見出しの書き方、文体など)
つまり、今後の検索においては「検索エンジンにどう解釈・要約されるか」を意識した**LLMO(Large Language Model Optimization)**的アプローチが必要になります。
こうした変化に対し、ジオコードでは早くからAIO・LLMOを見据えたSEO支援を強化しています。
たとえば
・LLMに適した構造と文脈設計:AIが“拾いやすく”“誤解しにくい”文章構造・文脈設計の支援
・ゼロクリック前提のブランディングSEO:表示されること自体にも注力し、認知・信頼につなげる設計
・SGE時代のトピック設計と情報粒度の最適化:生成AIに好まれる形式や表現手法への対応
今後は単に検索順位を上げるだけでなく、「AIに好かれる情報提供者」として、ユーザーの検索体験の中に自然と入り込んでいくことが重要です。
ジオコードではこのような最新の検索環境に対応したSEOサービスを通じて、企業のデジタルマーケティング戦略を支援しています。
これからのSEOには、次のような視点が不可欠です。
・「表示された瞬間に価値を届ける」発想への転換
・検索エンジンやAIに選ばれる構造、文脈設計
・ゼロクリックでもブランドを印象づけるブランディングSEO
・AIO、LLMOを見据えた最先端のSEO戦略
とくに、生成AIの進化により検索体験が急速に変化する中、SEO=単なる順位争いではなく、検索体験設計そのものになりつつあります。
ゼロクリック検索やAI Overviewsなどの新しい潮流にどう向き合うかお悩みの方は、ぜひジオコードのSEOサービスをご検討ください。